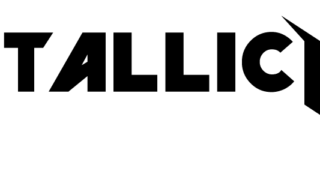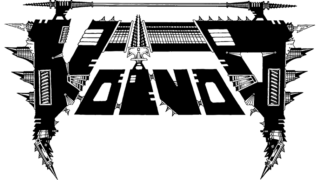Contents
- 1メンバーの死を乗り越えて熱狂的なファンを抱える世界有数のアリーナバンドの座に上りつめた大陸的ヘヴィ・ロックンロール・レジェンドは、欧米と日本での人気が伴わないスモール・イン・ジャパンの代表格!?
- 1...1ローカルバンドからワールドワイドな存在に!1
- 1...2AC/DCの音楽性は!?
- 1...3ヴォーカリストの死を超えてビッグに!?
- 1...4スモール・イン・ジャパンの代表的バンド!?
- 1.1AC/DC - ORIGINAL ALBUM|DISCOGRAPHY
- 1.1.1High Voltage| ハイ・ヴォルテージ
- 1.1.2T.N.T.|ティー・エヌ・ティー
- 1.1.3High Voltage| ハイ・ヴォルテージ
- 1.1.4Dirty Deeds Done Dirt Cheap|ダーティ・ディーズ・ダート・チープ:悪事と地獄
- 1.1.5Let There Be Rock|レット・ゼア・ビー・ロック:ロック魂
- 1.1.6Powerage|パワーエイジ
- 1.1.7Highway to Hell|ハイウェイ・トゥ・ヘル:地獄のハイウェイ
- 1.1.8Back in Black|バック・イン・ブラック
- 1.1.9For Those About to Rock We Salute You|フォー・ゾウズ・アバウト・トゥ・ロック・ウィ・サリュート・ユー:悪魔の招待状
- 1.1.10Flick of the Switch|フリック・オブ・ザ・スウィッチ:征服者
- 1.1.11Fly on the Wall|フライ・オン・ザ・ウォール
- 1.1.12Blow Up Your Video|ブロウ・アップ・ユア・ヴィデオ
- 1.1.13The Razors Edge|ザ・レイザーズ・エッジ
- 1.1.14Ballbreaker|ボールブレイカー
- 1.1.15Stiff Upper Lip|スティッフ・アッパー・リップ
- 1.1.16Black Ice|ブラック・アイス:悪魔の氷
- 1.1.17Rock or Bust|ロック・オア・バスト
- 1.1.18POWER UP|パワー・アップ
- 1.2AC/DC - OMNIBUS ALBUM|DISCOGRAPHY
- 1.2.1Who Made Who |フー・メイド・フー
- 1.2.2Iron Man 2|アイアンマン2
- 1.2.2.1◎ AC/DCはコレを聴け!! ライターおすすめアルバム!
メンバーの死を乗り越えて熱狂的なファンを抱える世界有数のアリーナバンドの座に上りつめた大陸的ヘヴィ・ロックンロール・レジェンドは、欧米と日本での人気が伴わないスモール・イン・ジャパンの代表格!?
AC/DC(エー・シー/ディー・シー)は、オーストラリア出身のハードロック/ヘヴィロック・バンド。
ローカルバンドからワールドワイドな存在に!1
AC/DCは、ハードロック全盛の1975年に、オーストラリアのローカルバンドとしてキャリアをスタートしており、当初はアルバムリリースも本国に限られていました。
のちに欧米で認められ、初期2作の楽曲から構成された国際版の『High Voltage』アルバムで世界デビューを果たし、ワールドワイドな活動に移行。
その後も着実に熱心なリスナーを開拓してゆき、現在では世界有数のハード/ヘヴィロック・バンドに数えられるビッグネームとなっており、2003年には『ロックの殿堂』入りも果たしています。
AC/DCの音楽性は!?
AC/DCの音楽性は、ブルーズロックやブギーをベースにした、大陸的なおおらかさを感じさせる、ミッドテンポ主体のヘヴィなロックンロールが基本スタイル。
本人たちもロックンロール・バンドを自認していますが、ヘヴィメタルの台頭やそのムーヴメントの広がりとともにその音楽性に接近して、シーンの趨勢に追従するかたちで知名度と人気を大きく高めたことから、ヘヴィメタルバンドとしても語られています、
そのあたりの意識と立ち位置については、MOTORHEADなどにも共通するものです。
また、AC/DCはやはりMOTORHEADらと同様に、どのアルバムもどの楽曲も作風に大きな変化が見られない、“金太郎飴”スタイルのバンドとして知られていますが、実際は、時期によって作風のマイナーチェンジも試みています。
AC/DCのキャリアを大まかに分けると、事故で急逝した初代ヴォーカリストのボン・スコットが在籍したいた第一期、それに代わって、ブライアン・ジョンソンがヴォーカルを務める現在までが、第二期以降となります。
ワイルドな歌唱スタイルのボン・スコットが在籍時は、ブルーズロックやブギーをベースにしたラフ&でアーシーなサウンドが持ち味としており、金属質のハイトーンヴォイスのブライアン・ジョンソン時代は、英国のヘヴィメタルムーヴメントやアメリカのメインストリームを意識して、それに合わせてサウンドも変化させていました。
そのため、オーソドックスなヘヴィメタル寄りのサウンドや、アメリカンハードロック路線、グラムメタル系のポップ路線など、その時期ごと…あるいはアルバムごとに、印象が異なる傾向も見られます。
ヴォーカリストの死を超えてビッグに!?
AC/DCは、バンドの世界展開が軌道に乗った矢先の1980年に、ヴォーカリストのボン・スコットが詳細不明の事故により急逝するという自体に見舞われ、活動の継続が危ぶまれました。
しかし、バンドは現在までフロントマンをつとめるブライアン・ジョンソンを後任に迎え、ヘヴィメタルのブームにも後押しされてさらなる飛躍を遂げ、世界でもトップクラスのスタジアム・バンドとして成功を収めます。
また、2016年には、ソングライティングも含めたバンドの中核でもあった、ギタリストのマルコム・ヤングが持病の悪化でリタイアとなり、翌2017年には他界しています。
この際も活動が危惧されましたが、後任にスティーヴィー・ヤング(ヤング兄弟との血縁ではない)を迎え、現在も活動を続けています。
スモール・イン・ジャパンの代表的バンド!?
AC/DCは、THE WHO(フー)などと並んで、日本国内と海外での人気の温度差が極端な『スモール・イン・ジャパン』系グループの筆頭格と見なされています。
欧米では連日ビッグアリーナを満員にする圧倒的な人気を誇っている反面、日本ではそれに見合う人気を得ることができす、通好みなバンドという立ち位置におさまっています。
そのため、50年に及ぶキャリアと世界的な知名度を誇るグループとしては、来日公演がわずか4度のみという異例の少なさとなっており、90年代にいたっては一度も来日公演を行っていないほどでした。
日本においては、人気マンガ『ジョジョの奇妙な冒険』の登場キャラクターで、彼らのバンド名に由来する名を持つ、『エシディシ』によって、AC/DCの存在を知った層の方が多いという説まで囁かれています。