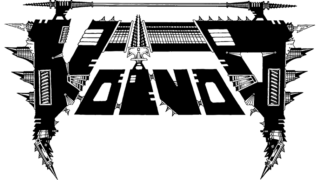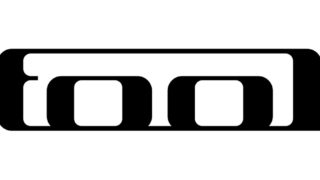Contents
- 1現代ジャーマン・メタル・シーンの代名詞となったバンドは、メロディック・パワーメタル/スピードメタルを完成させ、そのスタイルを世界中に波及させたレジェンドに!!
- 1...1ジャーマン・パワーメタルのパイオニア!?
- 1...2続々多様化するジャーマン・パワーメタル!?
- 1...3HELLOWEENとGAMMA RAYに分裂!?
- 1...4アグレッシヴからポップ&キャッチーへ!?
- 1...5メロディック・パワーメタルの現役リーダー!?
- 1.1HELLOWEEN|DISCOGRAPHY
- 1.1.1Walls of Jericho|ウォールズ・オブ・ジェリコ
- 1.1.2Keeper of the Seven Keys Part I|キーパー・オブ・ザ・セヴン・キーズ パート1:守護神伝 -第一章-
- 1.1.3Keeper of the Seven Keys Part II|キーパー・オブ・ザ・セヴン・キーズ パート2:守護神伝 -第二章-
- 1.1.4Pink Bubbles Go Ape|ピンク・バブルズ・ゴー・エイプ
- 1.1.5Chameleon|カメレオン
- 1.1.6Master of the Rings|マスター・オブ・ザ・リングス
- 1.1.7The Time of the Oath|タイム・オブ・ジ・オウス
- 1.1.8Better than Raw|ベター・ザン・ロウ
- 1.1.9Metal Jukebox|メタル・ジュークボックス
- 1.1.10The Dark Ride|ダーク・ライド
- 1.1.11Rabbit Don't Come Easy|ラビット・ドント・カム・イージー
- 1.1.12Keeper of the Seven Keys - The Legacy|キーパー・オブ・ザ・セヴン・キーズ - ザ・レガシィ:守護神伝 -新章-
- 1.1.13Gambling with the Devil|ギャンブリング・ウィズ・ザ・デヴィル
- 1.1.14Unarmed|アンアームド
- 1.1.157 Sinners|セヴン・シナーズ
- 1.1.16Straight Out of Hell|ストレイト・アウト・オブ・ヘル
- 1.1.17My God-Given Right|マイ・ゴッド・ギヴン・ライト
- 1.1.18Helloween|ハロウィン
- 1.1HELLOWEENはコレを聴け!! ライターおすすめアルバム!
現代ジャーマン・メタル・シーンの代名詞となったバンドは、メロディック・パワーメタル/スピードメタルを完成させ、そのスタイルを世界中に波及させたレジェンドに!!
HELLOWEEN(ハロウィン)は、ドイツのパワーメタル/ヘヴィメタルバンド。
ジャーマン・パワーメタルのパイオニア!?
80年代後半に世界的なブームとなって各国のメタルシーンに影響を及ぼした、いわゆる「ジャーマン・パワーメタル」のパイオニアとして知られるグループ。
祝祭ハロウィンでおなじみのカボチャマスク、『ジャック・オー・ランタン』をイメージキャラクターとしていることから、“カボチャ”の異名で呼ばれることもあります。
『ジャーマン・パワーメタル』は、現在では『メロディック・パワーメタル(メロパワ)』『メロディック・スピードメタル(メロスピ)』の名称で世界中に広がっており、HELLOWEENは当時よりそのシーンを代表するトップグループの地位にあります。
続々多様化するジャーマン・パワーメタル!?
現在でも、『ジャーマン・パワーメタル=メロディック・パワーメタル/メロディック・スピードメタル』は、ヘヴィメタルの主流ジャンルのひとつとして大きなシェアを誇り、いくつもの派生ジャンルを生んでいます。
この『ジャーマン・パワーメタル』からは、現在様々な派生ジャンルを産んでおり、ネオクラシカル系, シンフォニック系, ゴシック系, トラッド系など、その流れをくむ様々な回ジャンルが登場しています。
HELLOWEENとGAMMA RAYに分裂!?
当初は創始者のカイ・ハンセン(Gt.+Vo.)と初期メンバーのマイケル・ヴァイカート(Gt.)の二頭体制でしたが、のちにハンセンが健康上の理由で脱退したことから、実質的にはヴァイカート主導のバンドとなります。
その後ハンセンはシーンにカムバックするも、新たに自身がリーダーとなる新バンドGAMMA RAY(ガンマ・レイ)を結成。現在に至るまで、HELLOWEENとジャーマン・パワーメタル人気を二分するライバル的存在として活動を続けています。
アグレッシヴからポップ&キャッチーへ!?
デビュー当初のHELLOWEENは、初期のヘヴィメタルやNEOBHMなどのオールドスクールなヘヴィメタルに、スラッシュメタルのアグレッションを加えたサウンドを展開。この時期は、スラッシュメタルにカテゴライズされることもありました。
そこに、古典的なポップミュージックをはじめ、トラッド・ミュージックやローカル・ポップスなどに由来すると思しき、耳なじみのいいメロディをフィーチャーすることで、アメリカンパワーメタルとも全く異なる魅力を持つ、スピーディーなパワーメタルを確立します。
この、アニメソングにも例えられる、口ずさめるようなポップで勇ましいメロディを主体とした、疾走感あふれるパワーメタルは、欧州や南米を中心に人気を獲得します。
日本でもパワーメタルの本場アメリカのバンド以上の人気を獲得し、80年代〜90年代にはヘヴィメタルの新たなスタンダードとみなされるまでになっていました。
メロディック・パワーメタルの現役リーダー!?
メンバーチェンジの影響やバンドの意識の変化もあって、一時期は実験的なポップ・メタルを試みていた時期もありましたが、こういったサウンドのマイナーチェンジはあれど、現在に至るまで大きなブランクもなくコンスタントな活動を続けて、常に第一線でシーンを牽引してきました。
現在のシーンにおいては全盛期ほどの存在感は感じられませんが、各国のメタルシーンにHELLOWEENの影響が広がっていることは見て取ることできます。