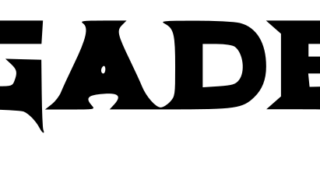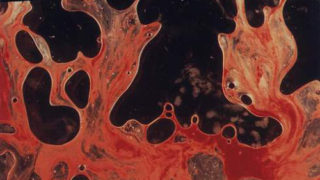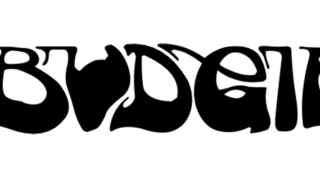Contents
- 1NSHC(ニュースクール・ハードコア)シーンで頭角を現してメタリック・グルーヴを極め、PANTERAの魂と90年代オールドスクール・グルーヴメタルを継承し、インスパイア街道をゆく“PANTERAクローン”の最右翼!!
- 1...1THROWDOWNは元祖メタルコア・バンド!?
- 1...2『グルーヴメタル』の伝統を受け継ぐメタルコア・バンド!?
- 1...3PANTERA系のグルーヴ・メタル・サウンドを追求!?
- 1...4PANTERAクローンを極めたTHROWDOWN!?
- 1...5THROWDOWNの現在の活動状況は!?
- 1.1THROWDOWN|DISCOGRAPHY
- 1.1.1Beyond Repair|ビヨンド・リペア
- 1.1.2You Don't Have to Be Blood to Be Family|ユー・ドント・ハヴ・トゥ・ビー・ブラッド・トゥ・ビー・ファミリィ
- 1.1.3Haymaker|ヘイメーカー
- 1.1.4Vendetta|ヴェンデッタ
- 1.1.5Venom & Tears|ヴェノム・アンド・ティアーズ
- 1.1.6Deathless|デスレス
- 1.1.7Intolerance|イントレランス
- 1.1.8Take Cover|テイク・カヴァー
NSHC(ニュースクール・ハードコア)シーンで頭角を現してメタリック・グルーヴを極め、PANTERAの魂と90年代オールドスクール・グルーヴメタルを継承し、インスパイア街道をゆく“PANTERAクローン”の最右翼!!
THROWDOWN(スロウダウン)は、ハードコアやスケートカルチャーのメッカとして知られる米国カリフォルニア州のオレンジカウンティを拠点とする、ストレートエッジ系のメタリック・ハードコア・バンド。
THROWDOWNは元祖メタルコア・バンド!?
THROWDOWNは、『N.S.H.C.(ニュースクール・ハードコア)』のムーヴメント末期に、そのシーンから登場したグループのひとつ。
この『N.S.H.C.』は、ハードコアとヘヴィメタルの双方の特徴的な音楽性を掛け合わせた、90年代ヘヴィミュージックのいちジャンルで、グルーヴメタルの流れを汲むヘヴィグルーヴや、スラッジコア/ドゥームメタルの影響下にあるダウナーなヘヴィネスを基調とした、スロー〜ミッドテンポ主体のサウンドが特徴です。
その音楽性から、『メタリック・ハードコア』と称されることもある『N.S.H.C.』は、スラッシュメタルとハードコアのハイブリッドとして80年代に一時代を築いた、『クロスオーバー・スラッシュ』の90年代版ともいえる存在で、現在まで続く『メタルコア』の直系のルーツにもあたり、そのシーンの母体となったジャンルでもあります。
THROWDOWNは、『N.S.H.C.』のシーンにおいては最後発のグループにだけに、デビュー時期が初期『メタルコア』の台頭とも近く、〈LAMB OF GOD〉〈AS I LAY DYING〉〈ILLSWITCH ENGAGE〉といった、後のメタルコア・ムーヴメントの中軸となるグループとは、ほぼ同時期のデビューであることから、それらと同様に『メタルコア』のパイオニアのひとつに数えられることもあります。
『グルーヴメタル』の伝統を受け継ぐメタルコア・バンド!?
『N.S.H.C.』〜『メタルコア』のジャンルにも、多くのスタイルが派生していることは周知の事実で、その中では、『メロデスコア』や『スクリーモ』などの叙情メロディ路線や、『ポスト・ハードコア』や『マスコア』などのプログレ路線、そしてメインストリームの『ニューメタル系』など、が主流をなしています。
これらが大半を占める同時期のグループの中で、THROWDOWNは例外的に、『グルーヴメタル/グルーヴコア』をベースにした、オーソドックスなストロング・スタイルの『メタリック・ハードコア』を展開していました。
その後も、むしろ彼らの前の世代にあたる『グルーヴメタル/グルーヴコア』のサウンドへと接近し、意識的に流行に逆行していくかのようなアプローチを展開してゆきます。
PANTERA系のグルーヴ・メタル・サウンドを追求!?
THROWDOWNは、グルーヴメタルのパイオニアであるPANTERAから多大な影響を受けていることで知られています。
バンドの音楽性も、ギタリストとして加入していたデイヴ・ピーターズが、2000年代に入ってリード・ヴォーカルを担当するようになってからは、初期のハードコア色の強いスタイルから、PANTERA系のグルーヴメタルを追求する傾向が顕著となります。
特に、PANTERAの活動停止となって以降というもの、それにタイミングを合わせたかのように、意識的に“PANTERAクローン”と呼ばれるようなスタイルへと接近、技巧に劣るものの系統はPANTERAのフィル・アンセルモに近いピーターズの歌唱も、それをより強く意識した“アンセルモ・クローン”スタイルの高みを目指してゆきます。
PANTERAクローンを極めたTHROWDOWN!?
その“PANTERAクローン”ぶりは『Vendetta(4th)』において頂点に極まり、ヴォーカル・スタイルのみならず、サウンド面においても、音づくりや曲調から、ギターのフレージングやリフワークに至るまで、徹底的にPANTERAスタイルをコピーし尽くした作風隣り、リスナーの間に賛否両論を巻き起こします。
その後もPANTERAテイストは維持しているものの、ヴォーカルスタル以外は通常のグルーヴメタル/グルーヴコアスタイルに戻っています。
THROWDOWNの現在の活動状況は!?
現在のTHROWDOWNは、すでに全パートが完全に代替わりしており、オリジナルメンバーはもはや1人も残っていませんが、現在もバンドはアクティヴな状態を維持しており、アルバムのリリースを含めた活動を継続しています。