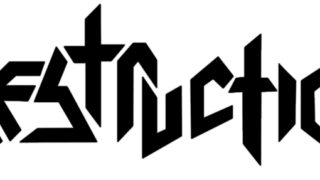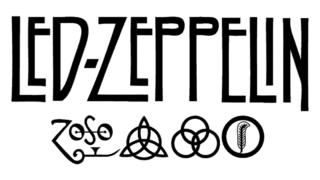Contents
音楽用語|ぶ|『ブレイクダウン:Break Down』』【音楽ジャンル・ムーヴメント】
このサイトで使われる用語で「どういう意味?」という疑問を受けたりしたワードを解説してゆく“音楽用語辞典”企画、今回のテーマは『ブレイクダウン』です!
ヘヴィミュージックにおける『ブレイクダウン』とは?
『ブレイクダウン』は様々な音楽シーン/音楽ジャンルで用いられるワードで、シーンによって微妙に定義は異なりますが、メタルやハードコアでは曲の中間部で極端にテンポを落とすことや、そのダウンテンポパートを指して使われます。
『ブレイクダウン』は『ビートダウン』や『スローダウン』、『スラミング』とも呼ばれています。
『ブレイクダウン』はモッシュタイム!?
一般的には『ブレイクダウン』はフロアにモッシュピットできてオーディエンスがここぞとばかりに大暴れする時間…モッシュタイム用のパートという認識が広がっています。
別称である『スラミング』は、これが“モッシュ=スラムダンス”をのために設けられたパートであることに由来します。
しかし、本当に暴れる人は通常パートから縦ノリでトバしまくっているので、『ブレイクダウン』はむしろテンションを落として息を整えるための一休みタイムになっていたりもします。
実際のところ、今は『ブレイクダウン』は「ハイ!みなさんココで暴れて〜」というマナーになっていますが、以前は『ブレイクダウン』になるとモッシュは一息ついて、サークルの中心でブレイクダンスよろしく入れ替わりたち代わりのハードコアダンス(手や足を振り回すダンス。最近はハーコーモッシュとも呼ぶ)バトルが繰り広げられるような、やや穏やかな時間でした。
最初からモッシュ目的だったわけではない!?
あたり前のことですが、ファストパートとスローパートのテンポチェンジを用いる手法は、『メタルコア』シーンで生み出されたわけではありません。
ロックシーンに限っても黎明期である60〜70年代から一般的でしたし、『メタルコア』のルーツである『クロスオーバー・スラッシュ』『デスメタル』『グラインドコア』『グルーヴメタル』『スラッジコア』などでも、一般的な手法として用いられていました。
ハードコアやパンクは“アンチ技巧主義”から、ひたすら同じテンポを続けるイメージがありますが、グループによっては積極的に以前からテンポチェンジを用いていました。
ただしこの時点までは、曲が単調にならないようにアクセントをつけたり、展開を複雑にして技巧性を追求するなど、あくまでも音楽性の工夫の一環という純粋にクリエイティヴな意図がありました。
『ブレイクダウン』はエクストリーム時代こそ活きる!?
前述のとおり、『ブレイクダウン』のテンポチェンジ手法自体は古典的なものです。しかし、90年代には“ファストの極み”であるデスメタル/グラインドコアと、“ダウナーの極み”であるドゥーム/スラッジが並び立つというエクストリームメタルシーンは“速遅両極時代”を迎えていました。
これらの影響を受けたことで、『ブレイクダウン』は過去最高にコントラストの極まったものとなり、聴き手により強いインパクトを与える手法となったことも確かです。
『ブレイクダウン』が定着!!
明確にオーディエンスのリアクションを意識して『ブレイクダウン=スローパート』を楽曲に導入するマナーが確立したのは、メタルコアの前身であるNSHC(ニュースクール・ハードコア)シーンと考えていいでしょう。
このあたりから、『ブレイクダウン』が“オーディエンスが特別なアクションを起こす時間”として本格的に定着。続く『メタルコア』ブームの中で、それがさらに広く認知されるようになり、ある種の“様式”として確立されます。
メジャー化/様式化が進んだ『ブレイクダウン』!?
最近は『ブレイクダウン』は“ライヴマナーの教科書”にものるくらい一般的になったため、オーディエンスを満足させるためのサービスとして無視できないものなってしまい、楽曲にも積極的に導入されるようになった結果、ノルマというか様式美のようなものになっており、スタイルの画一化を招いている傾向も見られます。