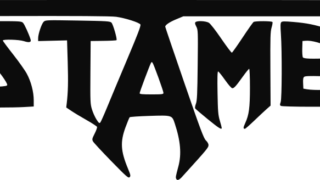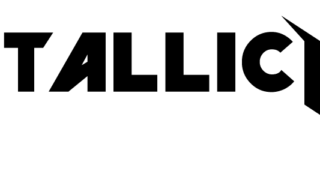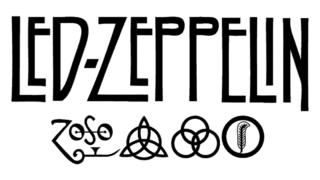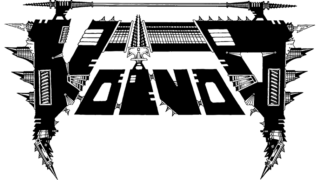Contents
- 1進化の停滞でヘヴィミュージックの飽和状態を迎えたゼロ年代に、個性的なメロディセンスと独自のハイブリッド手法で個性的なヘヴィ・サウンドを完成させた“ポスト世代”の奇才!!
- 1...1行き止まりの00年代型ハイブリッド・ヘヴィロック!?
- 1...2MASTODONは新世代プログレ!?
- 1...3MASTODONが属するポスト系ジャンルとは!?
- 1...4MASTODONは新世代NEUROSISチルドレン!?
- 1...5NEUROSISチルドレンの枠を超えて!?
- 1...6MASTODONサウンドの特性は!?
- 1...7ポップでキャッチーなサイケデリアを追求!?
- 1...8MASTODONの現在の活動は!?
- 1.1MASTODON|DISCOGRAPHY
- 1.1.1Lifesblood|ライフズブラッド
- 1.1.2Remission|リミッション
- 1.1.3Leviathan|リヴァイアサン
- 1.1.4Call of the Mastodon|コール・オブ・ザ・マストドン
- 1.1.5Blood Mountain|ブラッド・マウンテン
- 1.1.6Crack the Skye|クラック・ザ・スカイ
- 1.1.7Live at the Aragon|ライヴ・アット・ザ・アラゴン
- 1.1.8The Hunter|ザ・ハンター
- 1.1.9Live at Brixton|ライヴ・アット・ブリクストン
- 1.1.10Once More 'Round the Sun|ワンス・モア・ラウンド・ザ・サン
- 1.1.11Emperor of Sand|エンペラー・オブ・サンド
- 1.1.12Cold Dark Place|コールド・ダーク・プレイス
- 1.1.13Medium Rarities|メディウム・レアリティーズ
- 1.1.14Hushed and Grim|ハッシュド・アンド・グリム
MASTODON|DISCOGRAPHY
Lifesblood|ライフズブラッド

ミニアルバム:EP (2001年)
Remission|リミッション

オリジナルアルバム – 1作目 (2002年)
どこかで聴いたような既存のグループの要素が練りこまれた、多種多様な各種エクストリーム・ヘヴィ・ミュージックのハイブリッド・スタイル。
と言ってしまえばそれまでなのですが、特筆すべきは、ポストハードコア/メタルの始祖ともされる〈NEUROSIS〉からの影響が顕著な、“NEUROSISチルドレン”の第一世代であること。
そして、その〈NEUROSIS〉にも通じる、テクニカルでエクスペリメンタルなサウンドを志していることが、大きな特徴にもなっています。
この時点では、まだメロディ/歌メロは重視されておらず、ヴォーカルもデスメタルに近いダーティ・ヴォイスで、曲調もファストパートが目立ちます。
彼らの“ハイブリッド”な作風は、先鋭性/新奇性を持った手法が頭打ちとなり、既存の音楽を個々のセンスでブレンドして組み立てる手法をとらざるを得なくなった現在、独自性の有る無しに関わらず逃れることのできない宿命に近く、彼らを含めどんな優れた同時代のグループも例外ではありえません。
とはいえ、それも前提に設定された既存ジャンルに安易に押し込むのを躊躇する程度には、独自の“ジャンル配合レシピ”といったものがすでに確立されており、それだけでも評価に値するでしょう。
|ダウナー度:★☆☆☆☆
|プログレ度:★★★☆☆
|ヴィンテージ度:★★☆☆☆
|メロディ度:★☆☆☆☆
|総合評価:★★★★☆
通好み
Leviathan|リヴァイアサン

オリジナルアルバム – 2作目 (2004年)
やや楽曲の多様性が増して展開にも工夫が見られますが、基本的にはスタイルは前作から大きく変わるものではありません。
また、後に多くを占めるようになるクリーンヴォーカルも本作からお目見えしますが、まだほんの申し訳程度で、それを活かした独自のメロディラインについても未開発ということもあり、作品の印象に影響を及ぼすほどではありません。
そのため、往年のMASTODONスタイルはまだ完成には至らっておず、それが本格的に仕上がるには次作以降を待たなければいけませんが、テクニカルな変則リフワークについては往年に近い“らしさ”が見られ、基礎の部分は出来上がりつつあると言えるでしょう。
テクニカルな作風には、大雑把に分けて「①お上手ですねで終わるもの」、「②技巧だけで芸の域に達しているもの」、「③技巧が他の何かを生み出すために機能しているもの」…などがありますが、MASTODONあえて言えばは③。
ここでの複雑でトリッキーな演奏は、例えば〈MASHUGGAH〉や〈TOOL〉などのバンド、あるいはストーナーやジャムロックのように、ある種のトリップ感やトランス感を誘発させるものであり、そこからも、ここでのMASTODONサウンドを堪能するには、技巧に耳を凝らすよりも音に身を委ねる聴き方が最適解とも言えます。
|ダウナー度:★★☆☆☆
|プログレ度:★★★☆☆
|ヴィンテージ度:★★☆☆☆
|メロディ度:★☆☆☆☆
|総合評価:★★★★☆
入門盤 通好み 実験作
Call of the Mastodon|コール・オブ・ザ・マストドン

コンピレーションアルバム (2006年)
Blood Mountain|ブラッド・マウンテン

オリジナルアルバム – 3作目 (2006年)
メロディとクリーン・ヴォイスによる“歌”を、初めて大々的に本格的に導入したアルバム。
同時期にニューメタルのシーンにおいても、やはり歌もの系が幅を利かせていましたが、それられ大きく異なるのは、それが必ずしも山場の盛り上がりのためのキャッチーな“サビの歌メロ”には限らないということ。
楽曲を構成するいち要素として自然にその流れの中に組み込まれており、初期のリスナーでもこれまでの作風と同じ感覚で違和感なく聴くことができますし、よほどのメロディ・アレルギーでもなければ、セルアウトしたとして抵抗を感じるようなこともないでしょう。
むしろ、楽曲に表情を持たせることにより、楽曲に変化と緩急をつけて多様性を強化する要素として効果的に働いてさえいます。
結果的には、本作での本格的なメロディとエモーショナルな歌唱の導入によって、バンドをひとつ上のステージへ押し上げることにも成功したと言えるでしょう。
|ダウナー度:★★☆☆☆
|プログレ度:★★★★☆
|ヴィンテージ度:★★☆☆☆
|メロディ度:★★★☆☆
|総合評価:★★★★★
殿堂入り 代表作 入門盤 通好み 実験作
Crack the Skye|クラック・ザ・スカイ

オリジナルアルバム – 4作目 (2009年)
前作と比較しても、明確にメロディーラインや歌メロが強化されていますが、それらは、前作にも増して強烈な印象を残す特徴的なものとなっています。
とはいえ、ニューメタル/メタルコアなどの界隈で、同様のアプローチをとっていたグループがよく陥りがちだった、「サビの歌メロ以外の部分が単なるツナギとしか機能しておらず、曲調もワンパターン化が著しい」…といったマイナス傾向は見られません。
そのため、前作で開花した作風を基調として、そこにメロディによるフックがプラスされたものとして、さらなる個性の強化を評価することができます。
本作でのこの変化は、テクニカルデスやマスコアのような、激しさ重視の技巧系エクストリーム・メタルを求めるリスナーには不満でしょうが、彼らの新たなひとつのスタイルとして納得できる十分な魅力を備えていますし、これによってリスナーの裾野を広げることにつながったのも確かでしょう。
|ダウナー度:★★★☆☆
|プログレ度:★★★★☆
|ヴィンテージ度:★★☆☆☆
|メロディ度:★★★☆☆
|総合評価:★★★★★+
殿堂入り 代表作 入門盤 賛否両論 通好み 実験作
Live at the Aragon|ライヴ・アット・ザ・アラゴン

ライヴアルバム (2011年)
The Hunter|ザ・ハンター

オリジナルアルバム – 5作目 (2011年)
毎度お馴染みとなったMASTODON印のサウンドはここでも健在ですが、歌メロの比重が前作からさらに高まっており、全体的にマイルドでソフィスティケートされた印象が強まっているのが特徴。
しかし、その路線での完全に成功には至っているとまでは言えませんし、その他の側面から評価するにしても、エクストリームメタル, プログレ, ストーナー…など、どの方向においてもやや中途半端な印象を残す仕上がりです。
そんな中でも、メロウでドリーミーなサイケポップ調のT-04, T-13などは新しい試みとして成功しているといえますが、出来栄えの優れない曲については、そのヴォーカルスタイルも相まって〈オジー・オズボーン〉あたりの凡庸な曲を聴かされているような気分にもなってきます。
人気面では中期のピークともいえる時期であり、一般的には比較的高い評価を得ている作品なのも確かです。
しかし、“聴きやすい”というメリットを除けば、全盛期の作品では明確に1枚落ちることは否めず、彼ら本来のポテンシャルを考えるならば、評価はおのずと厳しいものとなってしまいます。
|ダウナー度:★★★☆☆
|プログレ度:★★★☆☆
|ヴィンテージ度:★★★☆☆
|メロディ度:★★★☆☆
|総合評価:★★★☆☆
代表作 賛否両論 スルメ盤
Live at Brixton|ライヴ・アット・ブリクストン

ライヴアルバム (2013年)
Once More ‘Round the Sun|ワンス・モア・ラウンド・ザ・サン

オリジナルアルバム – 6作目 (2014年)
『Blood Mountain(3rd)』に端を発した、歌モノ/メロディ路線としての最高峰にして、ひとつの到達点でもあるアルバムです。
全編にわたってフックの効いた魅力的なメロディラインや歌メロが満載で、メロディーや歌を本格的にフィーチャーするようになった直近2作と比較しても、その充実ぶりはケタ違い。
キャッチーなサビメロを楽曲のピークに持ってくる、メインストリームでよく見られるオーソドックスな手法も取り入れており、メロディや歌メロが楽曲の主軸として機能している曲も多く見られます。
エクストリーム・メタル界隈においては、こういったメロディーやポップネスの導入は、無条件にセルアウトと見なされてバッシングを受ける傾向がありますし、客観的に見ても賛否両論はやむを得ない面があります。
それでも、ここまでユニークで完成度の高いメロディを提示されれば、文句のつけようは無いでしょう。
むしろ、やや希薄だった明確な独自性を求めての、試行錯誤を繰り返していたMASTODONにとって、この印象的なメロディはそれに値する持ち味となっており、使い方さえ間違いなければテクニカルな演奏以上の大きな武器となり得るものであり、事実、ここではそれが大きくプラスに働いています。
|ダウナー度:★★★☆☆
|プログレ度:★★★★☆
|ヴィンテージ度:★★★☆☆
|メロディ度:★★★★★
|総合評価:★★★★★+
殿堂入り 代表作 入門盤 賛否両論 実験作
Emperor of Sand|エンペラー・オブ・サンド

オリジナルアルバム – 7作目 (2017年)
前作からの、本格“歌モノ路線”強化の推進が大きな影を落としているアルバムで、彼ら本来の特異性が、“プログレ風味”という部分を除くとかなり薄れており、“普通”のハードロック/ヘヴィメタルへと大接近ようなサウンドに仕上がっています。
彼らの独自の立ち位置を考えるなら、今回のこの変化は限りなくマイナスに傾きかねない要素として、“良くも悪くも”で済ますわけにもゆきませんし、そうでなくても、純粋にメロディーセンスや効果的な使い方の点において、前作には一歩およんでいません。
それでも、T-03,T-04,T-10のような従来路線での佳曲もあり、また、“普通のメタル路線”についても比較的高水準な仕上がりを見せているので、方向性が曖昧だったことで消化不良気味だった『The Hunter(5th)』と比較すれば、アベレージについてはかなり上回っています。
また、これまでの作品からはやや判断が難しかった、〈MUSE〉ら“00年代型UKポンプロック”に対応する“00年代型USプログレハード”という相似形が、ここに来て限りなく“普通”のプログレ風ハードロック/ヘヴィメタルに近付いたことで、かなり明確に目に見えるものとなりました。
|ダウナー度:★★☆☆☆
|プログレ度:★★★☆☆
|ヴィンテージ度:★★☆☆☆
|メロディ度:★★★☆☆
|総合評価:★★★★☆
入門盤 賛否両論
Cold Dark Place|コールド・ダーク・プレイス

ミニアルバム:EP (2017年)
Medium Rarities|メディウム・レアリティーズ

コンピレーションアルバム (2020年)
Hushed and Grim|ハッシュド・アンド・グリム

オリジナルアルバム – 8作目 (2021年)
MASTODONとしては初のCDにして2枚組の大ボリュームに仕上げられた本作は、2018年に癌で他界した元のマネージャー、ニック・ジョンへの追悼盤とアナウンスされたアルバム。
音楽性については、劇的な変化を遂げているわけでも、際立った特異性があるわけでもないのですが、ベーシックな部分は踏襲しつつも、全体の印象としては過去作とはやや印象を異にしています。
その要因のひとつとして挙げられるのは、変則的なテクニカル要素、圧倒的なヘヴィネス、トリッピーなサイケデリア、エモーショナルなメロディ…といった、従来のサウンド面の特徴で振り切って尖った部分がややおとなしくなり、エッジが取れてかなりまろやかなものになっていること。
これはオールドファンには賛否両論となるところでしょうが、時に〈VOIVOD〉に近いストレンジなアートメタル・センスを織り込みつつも、全体的には普通のプログレメタル/プログレハードに近づいているため、一般メタラー層への間口は広くなったと見ることもできるでしょう。
もうひとつは、メロディラインや曲調などにおいて、過去作とはひと味違ったものを取り入れた曲が目につくこと。
MASTODONの定番スタイルの確立以降は、アルバムによっては手癖に近いメロディの使い回しが目立つあたりが大きなネックとなっており、評価を下げざるを得ないケースもがありましたが、そういった面については、ここにきてかなり本気で取り組んだように見受けられます。
一方で、それらの試みの足を引っ張っているのが、やはりCD2枚組というボリュームと曲数。
トータル120分超えも珍しくないCD時代の2枚組アルバムとしては、15曲86分超の本作はそれほど過剰なボリュームというわけではないのですが、どうにも持て余しがちな気配が漂います。
聴きどころの無い凡曲でのカサ増しが目に余ることに加え、過去作ほどには強烈なフックやインパクトを持った曲が見られないこともあって、ひとつのアルバムとしては全体にフラットな印象が勝ってしまい、せっかくの貴重な佳曲や新機軸までもがそれに埋没しがち。
かといって“スルメ盤”と呼ぶにはもうひとつ旨味が足りないという、なんとも散漫でボンヤリとした残念な仕上がりとなっています。
|ダウナー度:★★☆☆☆
|プログレ度:★★★☆☆
|ヴィンテージ度:★★☆☆☆
|メロディ度:★★★☆☆
|総合評価:★★★★☆
賛否両論 スルメ盤 実験作