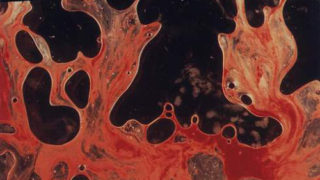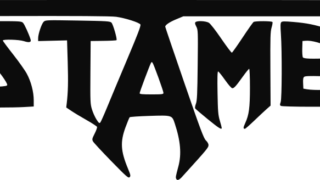Contents
- 1英国グラインドコアのパイオニアとして80年代からエクストリームミュージックシーンの最前線に立ち、常にリードし続ける実験精神あふれるカリスマグループ!!
- 1...1英国エクストリーム・シーンの最先端バンド!!
- 1...2NAPALM DEATH出身の重鎮たち!!
- 1...3ヘヴィメタルへの接近とさらなる進化!!
- 1...4ポリティカルで実験的な信頼のバンド!!
- 1.1NAPALM DEATH|DISCOGRAPHY
- 1.1.1Scum|スカム
- 1.1.2From Enslavement to Obliteration|フロム・エンスレイヴメント・トゥ・オブリタレイション:永続革命宣言
- 1.1.3Harmony Corruption|ハーモニー・コラプション
- 1.1.4Utopia Banished |ユートピア・バニッシュド:失楽園
- 1.1.5Fear, Emptiness, Despair|フィアー,エンプティネス,ディスペイア:哀歌
- 1.1.6Diatribes|ディアトライブス
- 1.1.7Inside the Torn Apart|インサイド・ザ・トーン・アパート
- 1.1.8Words from the Exit Wound|ワーズ・フロム・ジ・イグジット・ウーンド
- 1.1.9Leaders Not Followers|リーダーズ・ノット・フォロワーズ
- 1.1.10Enemy of the Music Business|エネミー・オヴ・ザ・ミュージック・ビジネス
- 1.1.11Order of the Leech|オーダー・オブ・ザ・リーチ
- 1.1.12Leaders Not Followers: Part 2h|リーダーズ・ノット・フォロワーズ:パート2h
- 1.1.13The Code Is Red... Long Live the Code|ザ・コード・イズ・レッド…ロング・リヴ・ザ・コード
- 1.1.14Smear Campaign|スミアー・キャンペーン
- 1.1.15Time Waits for No Slave|タイム・ウェイツ・フォー・ノー・スレイヴ:世界平和を願う。
- 1.1.16Utilitarian|ユーティリタリアン
- 1.1.17Apex Predator - Easy Meat|エイペックス・プレデター・イージー・ミート
- 1.1.18Throes of Joy in the Jaws of Defeatism|ゾーズ・オブ・ジョイ・イン・ザ・ジャムズ・ディフィーティズム:永遠のパラドクス
NAPALM DEATH|DISCOGRAPHY
Scum|スカム

オリジナルアルバム – 1作目 (1987年)
それぞれが革新的なアプローチでエクストリーム・ミュージック新時代の扉を開き、現在では各シーンのカリスマとして君臨する、CATHEDRALのリー・ドリアン(Vo.)、CARCASSのビル・スティアー(Gt.)、GODFLESHのジャスティン・ブロードリック(Gt.)、SCORNのミック・ハリス(Dr.)という、気鋭のアーティストが集結したデビューアルバム。
わずか1秒の最短のロック・チューン『You Suffer』が、「エッ!?何!?短かッ!!ウヒャヒャ(笑)」と何かにつけてネタにされるアルバムで、 他の曲を見ても2分以上は28曲中で3曲のみ、逆に1分以下の曲は作品中3分の1以上の12曲にものぼりますが、これはファストなハードコアとしては標準の範囲内です。
やや無邪気ともいえるプリミティヴな実験性には、確かに色物的な見方も避けられない部分はありますが、根本にあるのは、あくまでもポリティカルで至極まっとうなハードコアであり、それについてはこれ以降も変わりません。
後のゴアグラインドやポルノグラインドなどのような、“ネタ”としてのおバカなスカムサウンドを期待すると肩透かしかもしれません。
|ハーコー度:★★★★★
|実験度:★★★★☆
|ヘヴィネス:★★☆☆☆
|スピード:★★★★★
|総合評価:★★★★★
殿堂入り 代表作 通好み 実験作
From Enslavement to Obliteration|フロム・エンスレイヴメント・トゥ・オブリタレイション:永続革命宣言

オリジナルアルバム – 2作目 (1988年)
現在に至るまでNAPALM DEATHの中核として活躍する、シェーン・エンバリーの初参加アルバム。
前作からの参加メンバーとしては、リー・ドリアン(Vo.)、ビル・スティアー(Gt.)、ミック・ハリス(Dr.)が引き続き名を連ねています。
コンパクトなファストチューンを主軸にした基本的な作風は前作を踏襲しており、22曲で30分弱というトラックリストからもそれはうかがえますが、楽曲はブラッシュアップされ、確かな向上を見せています。
また、冒頭のT-01ではGODFLESHやSCORNにも通じるスロー&ダウナー楽曲にも挑戦しており、ただのマンネリズム追求には終わることのない今後の展開を予兆させます。
また、この最初期のエクストリームな実験精神と表現方法は、ジョン・ゾーンらをはじめとしたフリージャズ, ノイズ, エレクトロニカ, オルタナティヴ/ポストロックなどの、アバンギャルドな志向性のアーティストにも刺激を与えました。
これによって、エクストリーム・メタルとアバン・ミュージックのちょっとした蜜月状態が、しばし続くことになるのですが、現在のエクストリームなポスト系/エクスペリメンタル系の多くは、そのあたりの焼き直しに終始していると言ってもいいほどです。
|ハーコー度:★★★★★
|実験度:★★★★☆
|ヘヴィネス:★★☆☆☆
|スピード:★★★★★
|総合評価:★★★★★+
殿堂入り 代表作 入門盤 通好み 実験作
Harmony Corruption|ハーモニー・コラプション

オリジナルアルバム – 3作目 (1990年)
初期メンバーの、リー・ドリアン(Vo.)とビル・スティアー(Gt.)が脱退。
新たなフロントマンとしてBENEDICTIONに在籍していたバーニー・グリーナウェイ、ギターにミッチ・ハリスが就任して、現在の鉄壁のラインナップへと一歩近づいています。
本作は、メタル的な整合感がアップしたデスメタリックな作風となり、ハードコア的なプリミティヴィティが苦手なメタルリスナーにも大きくアピールするようになりました。
曲も大半が3分以上とデスメタルの平均レベルの長さになりましたが、実力者ぞろいだけに、ハードコアからメタルに移行したバンドに多い、「曲の長さを無駄に持て余して、ダラダラとリフを垂れ流すだけ」などということはなく、どの曲も緻密に組み立てたれてよく練りこまれています。
デスメタルとグラインドコアのクロスオーバーとしては、ひとつの頂点とも言えるアルバムの1枚です。
|ハーコー度:★★★★☆
|実験度:★★★☆☆
ヘヴィネス:★★★☆☆
|スピード:★★★★☆
|総合評価:★★★★★+
殿堂入り 代表作 入門盤 賛否両論 実験作
Utopia Banished |ユートピア・バニッシュド:失楽園

オリジナルアルバム – 4作目 (1992年)
ドラムがミック・ハリスからダニー・ヘレラへと代わったことで、アルバムデビュー以来のメンバーは総入れ替えとなり、現在まで続く鉄壁の布陣がそろい踏みとなった本作も、引き続きデスメタリックなグラインドコアを展開しています。
T-15はミック・ハリスのユニットSCORNの初期を思わせる、スローでダウナーなトラックですが、それ以外はほぼファストチューンで占められており、曲の長さも前作と比較すると全体的に短め。作風も、初期に近いストレートなものとなっています。
作品としては高水準で、一気に聴きとおせる爽快なアルバムですが、やや単調に感じられる面もあり、現状のスタイルとしては手詰まり感も漂っています。
次作以降、新たなアプローチを試みて攻めた作品を連発するのも、必然的な流れといえるでしょう。
|ハーコー度:★★★★☆
|実験度:★★★☆☆
|ヘヴィネス:★★★☆☆
|スピード:★★★★☆
|総合評価:★★★★★
入門盤
Fear, Emptiness, Despair|フィアー,エンプティネス,ディスペイア:哀歌

オリジナルアルバム – 5作目 (1994年)
デビュー以来のスピード追求型の作風から、ミッド〜スローテンポのパートを多用したヘヴィグルーヴを導入した、新たなスタイルに移行したやや実験的なアルバム。
ドゥーム/スラッジに近いテイストや、次作で顕著となるマシーナリーでスペーシー音づくりも、この時点から確認することができます。
わかりやすい勢いや派手さはないものの曲はよく寝られており、時にはテクニカルでトリッキーな変則展開も顔をのぞかせます。
適度なフックの効いたフレーズも多く見られるのですが、それを考慮してもやや地味にも感じられる通好みな作風は、好みが分かれるところかもしれません。
事実、当時は賛否両論で、本作が迷走期への突入とされることもありますが、さらに攻めたアプローチを見せた次作に最強問題作の座を奪われ、相対的に良くも悪くも印象が薄くなってしまいました。
いずれにせよ、本作から数作のアプローチがグラコア回帰以降の作品に果たした影響の重要性は、決して無視できないものです。
|ハーコー度:★★★☆☆
|実験度:★★★☆☆
|ヘヴィネス:★★★★★
|スピード:★★★☆☆
|総合評価:★★★★★
殿堂入り 賛否両論 通好み スルメ盤 実験作
Diatribes|ディアトライブス

オリジナルアルバム – 6作目 (1996年)
いわゆる“ナパムデ迷走期”第2弾の本作は、その中時期でも次作(7th)と共にNAPALM DEATH史上最大の問題作とされ、実験性や変化を好まない保守的なグラインドコア/デスメタル・クラスタはもちろん、前作(5th)までは許容していたリスナーからも総スカンを食らったアルバムです。
グルーヴメタルやニューメタルなどの、当時の最前線だったUSモダンサウンドをも取り入れており、特に、FEAR FACTORYあたりに通じるようなモダン・インダストリアルのテイストが濃厚に感じられます。
米国トレンドに接近したようにも思える、ダンサブルなアッパー感やグルーヴに満ちた作風は、当然のごとくリスナーからは批判一色でしたが、そもそものバンドの姿勢や立ち位置を考えれば、そういった偏狭さは鼻で笑われるだけでしょう。
もはや、純グラインドコアでもデスメタルでもないとはいえ、独自のセンスに満ちあふれた本作は、NAPALM DEATHにしかつくり出しえない名盤と言えます。
|ハーコー度:★★★☆☆
|実験度:★★★★☆
|ヘヴィネス:★★★★★
|スピード:★★★☆☆
|総合評価:★★★★★+
殿堂入り 賛否両論 通好み 実験作
Inside the Torn Apart|インサイド・ザ・トーン・アパート

オリジナルアルバム – 7作目 (1997年)
迷走期4部作の第3弾となる本作は、最大の問題作とされる前作“Diatribes”を踏襲しつつ、ブラッシュアップしたような作風です。
定番のグラインドコア・スタイルを押しのけての新機軸や、洗練された整合感の強いサウンドが特徴であるため、実験性や整合感を好まない保守的なハードコア/メタルクラスタからは、前作同様に黒歴史として無視され続けています。
とはいえ、そもそも本来のNAPALM DEATH自体が、グラコア様式美に則った後発バンドとは異なり、音楽的実験の結果そのスタイルにたどり着いた“実験性の塊”のようなグループなので、その批判もお門違いでしょう。
現在に至るまで、無難な定番サウンドの繰り返しに終始せずプログレスしてこられたのも、ここでの試みがあったればこそです。
何より、前作同様に完成度の高さには目を見張らずにはおれない充実の名盤ですし、後にオーソドックスなグラコア主体のアプローチに回帰して以降にも、この時期のエッセンスは確実に反映されています。
|ハーコー度:★★★☆☆
|実験度:★★★☆☆
|ヘヴィネス:★★★★★
|スピード:★★★☆☆
|総合評価:★★★★★+
殿堂入り 入門盤 賛否両論 通好み 実験作
Words from the Exit Wound|ワーズ・フロム・ジ・イグジット・ウーンド

オリジナルアルバム – 8作目 (1998年)
迷走期4部作呼ばれる一連の作品のトリを飾るアルバムですが、前2作に顕著なマシーナリーでスペーシーなサウンドとヘヴィグルーヴを踏襲しつつも、グラインドコアへの回帰傾向を予感させるようなファストパートが増えています。
結果的に、ここ時期の新機軸路線の中では、比較的オールドファンにも受け入れやすい作品となりました。
ただし、そのファストチューンも基本的には前作までの延長上にあるスタイルなので、あくまでもストレートなグラインドコアにこだわる向きにはお呼びではないでしょう。
そこがクリアできるなら、品質は高水準安定でストレスなく聴けるので安心してオススメできますが、この直近の2作(6thと7th)がウェルカムなリベラルな感性のリスナーにとっては、逆に無難すぎて変化に乏しく攻めが足りないように映るかもしれません。
|ハーコー度:★★★☆☆
|実験度:★★★☆☆
|ヘヴィネス:★★★★★
|スピード:★★★★☆
|総合評価:★★★★★
入門盤 賛否両論 通好み スルメ盤
Leaders Not Followers|リーダーズ・ノット・フォロワーズ

カバーミニアルバム (1999年)
ハードコアやスラッシュ/デスメタルなどの初期作品を中心に取り上げてカバーした、トリビュート・ミニアルバム。
90年代半ばからのトリビュート・アルバムのブーム流れにある企画ですが、本作が好評で、第二弾としてフルレンス・アルバムまでがリリースされる運びとなりました。
|ハーコー度:★★★★☆
|選 曲:★★★☆☆
|意 外 性:★☆☆☆☆
|アレンジ:★★★☆☆
|総合評価:★★★★☆
入門盤 賛否両論 通好み
Enemy of the Music Business|エネミー・オヴ・ザ・ミュージック・ビジネス

オリジナルアルバム – 9作目 (2002年)
オールドファンが期待するような、ファストなグラインドコア路線へと回帰したアルバム。
とはいえ、何から何まで最初期のスタイルというわけではなく、この直近数作に近いサウンドメイクで3rd, 4thの頃のデス/グラインドコア路線を展開したような作風です。
楽曲も整合感を重視したつくりが主体で、長さも平均3分程度と極端に短いわけではありません。
ここにきて、前4作でのヘヴィグルーヴ/インダストリアルテイストの試みの不評を受けての原点回帰は、かなり安易な安パイ戦略とも思えますし、実験性の薄さは物足りなく感じられます。
とはいえ、爽快なほどに圧倒的なスピードチューンに徹して作り込まれたアルバムとして、完成度の高さは否定しようがありません。
また、その原点回帰の印象の強さの影に隠れて目立たないものの、直近数作で見せたマシーナリーなサウンドやヘヴィグルーヴも楽曲に活かされているなど、そこでの試みは確実に本作もにつながっており、評判の悪い黒歴史期間も無意味な路線変更ではなかったことが確認できます。
|ハーコー度:★★★☆☆
|実験度:★☆☆☆☆
|ヘヴィネス:★★★★☆
|スピード:★★★★★
|総合評価:★★★★★
代表作 入門盤
Order of the Leech|オーダー・オブ・ザ・リーチ

オリジナルアルバム – 10作目 (2002年)
前作に続き、アルバム全編にわたって徹頭徹尾ファストチューンが満載で、さらに、これまでになくヘヴィメタル・テイストの濃厚なサウンドが特徴的な作品。
速さ一筋のスタイル自体は前作同様ではあるものの、作風自体はそれなりに変化に富んでおり、ここでは、ネオスラッシュ/デスラッシュ風やブラックメタル風など、多様なエクストリーム・メタルのスタイルを取り入れたアプローチを見せています。
とはいえ、それらのメタルジャンルそのままのサウンドをダイレクトに持ち込んだわけではなく、その特徴的なエッセンスだけ取り出して、本来のグラインドコア・サウンドとのクロスオーバーを試みており、ひとひねり加えたNAPALM DEATHならではのアレンジが施されています。
その作風がら、好みが分かれがちな傾向ははやむを得ないところではあるものの、クオリティ自体は折紙付の高品質“ナパムデ印”。さすがに、これが毎度のように続いては飽きてしまいますが、1作程度であれば変化球としてアリと判断できるだけの仕上がりを見せています。
|ハーコー度:★★★☆☆
|実験度:★☆☆☆☆
|ヘヴィネス:★★★★☆
|スピード:★★★★★
|総合評価:★★★★☆
代表作 入門盤 賛否両論 実験作
Leaders Not Followers: Part 2h|リーダーズ・ノット・フォロワーズ:パート2h

カバーフルアルバム (2004年)
ミニアルバムでのカバー集だったパート1に続いて、全19曲の特大ボリュームでリリースされたトリビュート・カバーアルバム。
やはりハードコア/スラッシュ/デス系中心で、メタラーにも知名度が高いバンドとしては、CRYPTIC SLAUGHTER, HELLHAMMER, ANTI-CIMEX, DISCHARGE, MASTER, KREATOR, MASSACRE, AGNOSTIC FRONT…といったところ。
ミニアルバムも同様でしたが、NAPALM DEATHテイストにアレンジされてはいるものの、良くも悪くも彼らのサウンドにピッタリとハマる曲ばかりなので、こちらの想像を大きいく超えていくことはありません。
その意味では、SLAYERのハードコア・カバーアルバムに近い印象があり、やはりストレートなアレンジながら、強烈な個性で全くカラーの異なるサウンドを自分色に染め上げたPRONGなどとは対局的。
カバーアルバムに何を求めるかで、評価が変動するアルバムと言えます。
|ハーコー度:★★★★☆
|選 曲:★★★★☆
|意 外 性:★☆☆☆☆
|アレンジ:★★★☆☆
|総合評価:★★★★☆
入門盤 賛否両論 通好み
The Code Is Red… Long Live the Code|ザ・コード・イズ・レッド…ロング・リヴ・ザ・コード

オリジナルアルバム – 11作目 (2005年)
ブラストの効いたファストチューンが立て続きに繰り出されますが、今回はメタルテイストはやや抑えめな、比較的ストレートなハードコア寄りの作風で、初期のクラスト/ファストコアをベースにしたサウンドに近い質感です。
ラストの2曲は、過去にも時折見せてきたGODFLESHやSCORN風のダウナーでアトモスフェリックなナンバー。
アルバム・オリエンテッド見方をすると、本作はやや無難かつフラットな印象が強いので、こういった曲を中盤にうまく組み込めばメリハリがつくのですが、ノンストップ・スピードチューンを満喫したいリスナーも存在するので、そこは悩ましいポイントかもしれません。
また、本作ではゲストヴォーカルとして、メタルコアバンドHATEBREEDのジェイミー・ジャスタがT-06, T-08、USハードコアの父DEAD KENNEDYSのジェロ・ビアフラがT-07、CARCASSのジェフ・ウォーカーがT-12で参加。
特にビアフラとウォーカーは、短いパートながらもさすがの存在感を見せています。
|ハーコー度:★★★★★
|実験度:★★☆☆☆
|ヘヴィネス:★★☆☆☆
|スピード:★★★★★
|総合評価:★★★★★
代表作 入門盤
Smear Campaign|スミアー・キャンペーン

オリジナルアルバム – 12作目 (2006年)
元THR GATHERINGのゴシックメタルの歌姫アネクをフィーチャーという、予想外の人選にびっくりのゴシカル・シンフォなT-01が予感させるとおり、00年代突入して以来、初めて本格的な攻めの姿勢を見せたアルバムと言えます。
ラスト直前まで豪速球一本やりだった前作と比較すると、本作ではスピード・チューンを基調としつつも、変化球による緩急がついた表情豊かな作風となっています。
定番のクラストベースの曲だけではなく、デス/スラッシュ的なリフワークを用いた曲もあり、またミッドテンポのヘヴィグルーヴ・パートを織り交ぜたり、スペーシーなSEをアクセントとして効果的に用いるなど、曲展開にも平坦にならないような工夫が凝らされています。
また、シェーン・エンバリーによるクリーンヴォイスの出番はそれほど多くはないものの、メインのバーニー・グリーナウェイとミッチ・ハリスの高音シャウトのツインヴォーカル・パートは、効果的なアクセントとして多用されています。
こういった作風の本作を、メタルコアのブームを引き合いに語りたい向きもあるかもしれませんが、むしろ、迷走期と呼ばれる時代も含めた過去の総決算として捉えるべきでしょう。
|ハーコー度:★★★☆☆
|実験度:★★★☆☆
|ヘヴィネス:★★★★☆
|スピード:★★★★☆
|総合評価:★★★★★
殿堂入り 代表作 賛否両論 通好み 実験作
Time Waits for No Slave|タイム・ウェイツ・フォー・ノー・スレイヴ:世界平和を願う。

オリジナルアルバム – 13作目 (2009年)
スピードチューンを基調として、過去の全てのキャリアを総括した総決算的な作風。…という意味では前作と同様なのですが、ここではそれを推し進めた上でさらに一歩大きく踏み込んでいます。
デス/スラッシュ/グルーヴ/インダストリアル/アンビエントなどのエッセンスはもちろん、ポスト系プログレに近い変則的な展開を多用した、テクニカルで凝った作風へのアプローチを見せており、これらの試みのすべてが、見事なまでに高いレベルで結実されています。
前作と並んで、後期作品の中でも“音楽的な実験性”と“楽曲の充実度”の両面においては、特に突出した完成度を実現した充実の1枚で、エクストリーム/エクスペリメンタルを志向する幅広いリスナーが、手に取るべきマスターピースと言えるでしょう。
|ハーコー度:★★★☆☆
|実験度:★★★☆☆
|ヘヴィネス:★★★★☆
|スピード:★★★★☆
|総合評価:★★★★★+
殿堂入り 代表作 賛否両論 通好み 実験作
Utilitarian|ユーティリタリアン

オリジナルアルバム – 14作目 (2012年)
前作での、比較的わかりやすいプログレ/ポストロック・アプローチから、より変則的でフリーキーなエクスペリメンタルな方向へ向かったアルバム。
とはいえ、様々な展開を挟みつつも冗長さ全くは微塵も感じさせることがなく、テンションとスピード感が一切落ちることはありません。
ときおりどこかで聴いたようなフレーズも混じってきますが、独特の音づくりやオーソドックスから外れ過ぎた組み立て方といった、独自のセオリーが根本にあるため、最終的には完全にオンリーワンの“ナパムデ印”に仕上がっています。
なお本作では、アンダーグラウンドなフリージャズ/アバンギャルドシーンの大物、ジョン・ゾーンが、T-03でサックスでゲスト参加。
ゾーンは、創世記のメンバーだったミック・ハリスらと、アバンギャルド&エクスペリメンタルなプロジェクトPAINKILLERを結成するなど、エクストリーム・メタルシーンとも縁の深い重要人物のひとりです。
|ハーコー度:★★★☆☆
|実験度:★★★☆☆
|ヘヴィネス:★★★★☆
|スピード:★★★★☆
|総合評価:★★★★★+
殿堂入り 代表作 賛否両論 通好み 実験作
Apex Predator – Easy Meat|エイペックス・プレデター・イージー・ミート

オリジナルアルバム – 15作目 (2015年)
数作おきに揺り戻しを起こしたようにリリースされる、初期に近いハードコア色濃厚なストレートなグラインドコア路線を狙ったようなアルバム。
それに合わせてか、サウンドの質感もパンキッシュでジャンクな荒々しいローファイ・テイストになっており、最初期の作品を除けば、特にハードコア色が強い印象を与える仕上がりです。
ただでさえ近年は、デス/スラッシュ系のリフワークを積極的に用いるなど、大胆にヘヴィメタルに寄ったアプローチ傾向が目立っただけに、そのに不満を感じていたリスナーも少なくないことは確か。
そのため、“あえてこの音づくり”であつらえたものとはいえ、このたぐいのアングラ風サウンドを歓迎する層が存在するのは間違いないところです。
とはいえ、近年のキャリアを総括するような集大成的作風についても、完全にに封印されたわけではなく、エクスペリメンタルなアプローチやスペーシーなインダストリアルエッセンスなどは、抑え気味ではあるものの健在です。
楽曲/アルバムのグレード自体は、毎度のように高水準安定なので、音づくりにさえ抵抗がなければ問題なく楽しめるでしょう。
|ハーコー度:★★★★☆
|実験度:★★☆☆☆
|ヘヴィネス:★★★☆☆
|スピード:★★★★☆
|総合評価:★★★★★
代表作 入門盤
Throes of Joy in the Jaws of Defeatism|ゾーズ・オブ・ジョイ・イン・ザ・ジャムズ・ディフィーティズム:永遠のパラドクス

オリジナルアルバム – 16作目 (2020年)